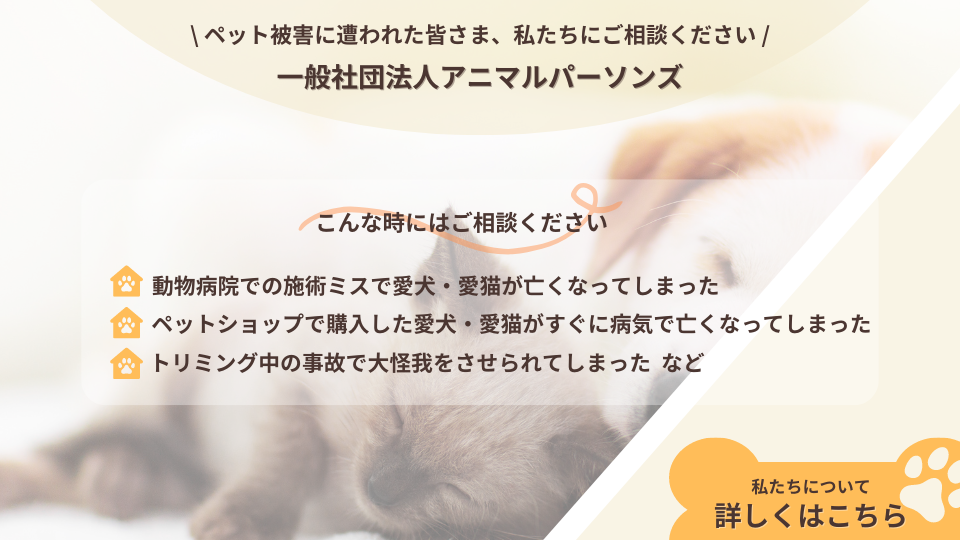本件で損害賠償請求が認められた理由|獣医師や動物病院が負う法的責任
ここでは、本件で損害賠償請求が認められた理由について解説します。
必要のない手術を施した
本件において手術・治療を受けた雌犬(以下、「A」といいます。)は、獣医師Bが経営する動物病院(以下、「C動物病院」と言います。)での初診時では15歳と高齢であるものの、これまで大きな病気をすることなく、飼い主3名のもとで健康な日常生活を過ごしていました。
下顎切除手術の必要性について
C動物病院に勤務する獣医師Dは、Aの初診時に口腔腫瘍が下顎骨を侵していると疑い、口腔腫瘍ならば下顎骨切除の手術をしなければならないと判断しました。
腫瘍が良性か悪性かによって、手術時の切除範囲や犬の顔の外見だけでなく、手術後の再発や遠隔転移のリスクが大きく異なります。そのため、腫瘍が良性か悪性かを確定するためには、腫瘍の組織を採取して生検検査を行う必要があるところ、獣医師Dは下顎の先端部分及び両下顎リンパ節に針生検を試みました。
下顎の先端部分には硬固な組織が存在し、組織の採取ができませんでしたが、両下顎リンパ節からは組織を採取し、腫瘍細胞のない正常なリンパ節であることが確認されました。つまり、この時点では、仮に腫瘍が悪性でも、下顎リンパ節まで転移していないことが分かっていました。
獣医師Dは、下顎の先端部分の腫瘍組織の生検を行うために、2つの方法を考えました。
一つはコア生検と呼ばれる方法で、麻酔をかけて一定量の組織を採取し、生検を行います。この方法では、もし悪性であると判明した場合は、さらに広範囲な下顎骨切除が必要になりますが、良性であれば切除範囲は狭くなります。
もう一つの方法は、治療と診断を兼ねた下顎骨切除です。ある程度広範囲に切除し、切除した部分を生検に提供します。この方法では、広範囲に切除する必要がありますが、一度の麻酔手術で済む利点があります。
獣医師Dは、この2つの方法のうち、後者を選択することを考えました。獣医師DはAの飼い主らに対して、腫瘤の増大の可能性を考慮し、下顎の一部(犬歯後方レベルまで)を切除し、その後に生検を行って悪性度を判定し、手術後の治療方針を決定すると説明しました。切除によって顔の外観が大きく損なわれることはないとも伝え、手術の承諾を求めました。
下顎骨切除の手術そのものは成功しましたが、Aの下顎のほぼ半分が切除され、Aの顔の形状が大きく変わっていることに飼い主らは驚きました。
さらに、獣医師Dはこの手術の目的である切除部位(腫瘤部分)の生検を行いませんでした。
裁判所は、「生検を行わない単に切除のみを目的とした不適当なものであった」と判断し、下顎骨切除手術の必要性を否定しました。
卵巣子宮全摘出手術の必要性について
獣医師Bおよび獣医師Dは、獣医師Dが2度目の診察の際に行った超音波(エコー)検査から、Aに子宮蓄膿症が確認されたと主張しました。獣医師Dによれば、初診時には子宮蓄膿症を疑わなかったものの、Aが避妊手術をしておらず出産経験のない犬であるため、「もしかしたら」という考えで腹部を剃毛せずに超音波検査を行ったところ、初期の子宮蓄膿症であることが確認されたと述べています。
しかし、診察日の詳細な内容やエコー検査の結果は証拠として残されておらず、血液検査においては、子宮蓄膿症の診断の重要な検索項目の一つとされているALP(アルカリホスファターゼ)検査も行われていませんでした。
Aの手術前の状態には臨床的な症状はなく、血液検査の結果も基準範囲内であり、異常は認められませんでしたが、獣医師Dは上記エコー検査の結果、直ちに卵巣子宮全摘出手術を行うことを決定しました。
この日、飼い主らは自家用車の都合がつかず、C動物病院のスタッフが運転する車にAだけを乗せてC動物病院に連れて行きましたが、あらかじめ診察の目的は告げられていませんでした。獣医師Dは、電話連絡をしてきた飼い主らに対し、直ちに手術をすべきと説得しました。
後日、飼い主らは卵巣子宮全摘出手術の説明を受けるために、C動物病院に来院しましたが、獣医師Dは、主に子宮蓄膿症について説明し「そのままにしておくと死に至る病気であり、緊急に卵巣子宮全摘出の手術が必要」と勧め、飼い主が納得したため手術が行われました。
卵巣子宮全摘出手術そのものは成功し、退院までに抜糸も済みましたが、獣医師Dが子宮摘出後に、子宮の膨張の程度や子宮の中にたまった膿を確認したことは証拠上認められませんでした。
裁判所は、獣医師Dの「子宮蓄膿症の診断は慎重を欠き不適正であり、また手術の緊急性の判断についても慎重さを欠き不適切であった」と判断し、卵巣子宮全摘出手術の必要性を否定しました。
乳腺摘出手術の必要性について
獣医師Dは、初診時にAの腹部、左第1乳頭部に腫瘤を確認したものの、重要視していませんでした。手術日に同腫瘤の針生検を行い、それが良性のものであると診断したにもかかわらず、卵巣子宮全摘手術のため開腹するついでに、同乳腺の腫瘤を除去しようと判断し、実施しました。
裁判所は、「乳腺摘出手術は簡易な手術であって附随的なものではあるけれども、良性のものそのまま放っておいても良かったもの」として、乳腺摘出手術の必要性を否定しました。
3箇所の手術を同時に行ったことについて
獣医師Bおよび獣医師Dは、麻酔手術の危険性を主張し、一度の麻酔で3箇所の手術を同時に行った本件の手術は適切であったと主張しました。
確かに、麻酔手術の危険性を考慮すれば手術の回数を最小限にすることが重要ですが、老犬のAにとっては、死の危険性が極めて高くなります。
獣医師Dは、飼い主らが手術に消極的なのを熟知していたのだから慎重に判断すべきだったのに、麻酔の危険性を考えるあまり同時手術の危険性を考慮せず本件手術を行いました。裁判所は、獣医師Dが行った本件手術およびそれに伴う治療行為は適切でなかったと判断しました。
なお、裁判所は、Aの手術後、獣医師Dが急に退職したことで、Aの治療について適切な引き継ぎがなされなかったことで、C動物病院で適切な治療が行われなかったとの飼い主らの主張については、C動物病院での措置が不適切であったことを認めるに足る証拠はないと判断しました。
飼い主が十分に理解した上で意思決定ができるだけの説明をなさなかった
本件の判決の中で、裁判所は、獣医師の説明義務について、「手術にあたって、獣医師は、原則として、飼い主の意思に反する医療行為を行ってはならず、飼い主が医療行為の内容や危険性等を十分に理解した上で意思表示できるよう必要な範囲の事柄を事前に説明する必要があり、人間と飼い犬の生命が問題となる場合とでは医師または獣医師が負う説明義務は全く同一の基準が適用されるべきではないにしても、一定の場合には、その説明の不履行が説明義務違反として飼い主に対し法的な責任を負担しなければならない場合がある」と言及しています。
本件では、Aのカルテや検査結果、手術に関する同意書(宣誓書)等が獣医師Bによって廃棄され、C動物病院に保存されていませんでした。その上で、裁判所は、下顎骨説切除手術および卵巣子宮摘出手術の実施については、飼い主の同意を得たものと認めつつ、「十分な説明を受けた上での真正な同意とはいえない」と判断しました。下顎骨切除手術については、切除の範囲やその結果について、一般人が具体的に認識できるような説明がされておらず、説明義務違反があったと認めました。
乳腺摘出手術についても、「良性の説明、そのまま放っておいて良いと判断された乳腺腫瘍の治療としての乳腺摘出手術は説明、同意を欠いたままされた」ものとし、獣医師Dに説明義務違反があったと認定しました。
補足|本件判決の内容
本件判決は、獣医師Dは、「不適切な本件手術(下顎骨切除手術、卵巣子宮全摘出手術)を行ったことについて、また、その際の下顎骨切除手術についての説明は前記のとおり具体性を欠くもので説明義務に反するもので、従って、それに基づく同意も真正な同意とは認められない点について及び説明と同意なしにそのまま放っておいても良い乳腺摘出手術をしたことについて、不法行為に基づき損害賠償責任を負い」、獣医師Bは獣医師Dの「使用者として、民法七一五条により損害賠償責任を負う」ものとし、獣医師Bおよび獣医師Dに対して、連帯して、飼い主らの以下の損害を賠償すべきと判示しました。
- 治療費相当額(飼い主1名につき59,406円×3名分=17万8,218円)
- 慰謝料(飼い主1名につき35万円×3名分=105万円)
- 弁護士費用(飼い主1名につき5万円×3名分=15万円)
なお、飼い主は、新たな犬の購入費40万円も支払うように主張しましたが、裁判所は、Aが15歳の老犬であったことを重視して新たな犬の購入費の支払いは認めませんでした。
勤務獣医師や勤務動物看護士の獣医療過誤と動物病院の責任
ここでは、使用人である獣医師や動物看護士が獣医療過誤を発生させた場合、動物病院の経営者はどのような責任を負うのかについて、3つのパターンを例に解説します。
使用人である獣医師による獣医療過誤が生じた場合|使用者責任
使用人である獣医師の診療行為や動物看護師の補助行為等が動物に被害を与えた場合、使用者は責任を問われます。このとき、勤務獣医師の不法行為が、使用者(動物病院の経営者)である獣医師の面前で行われたものでなくても、使用者である獣医師の責任は免れません。
使用者に代わって使用人を監督する立場にあった院長や部長等も使用者責任を問われることがあります。
使用者責任を免れる、あるいは軽減されるためには、従業員の選任や業務の監督等について相当な注意を払い、なお相当の注意をしても、獣医療事故の発生を免れ得なかったことを証明する必要があります。
複数の獣医師が共同して診療を行った結果、過誤が生じた場合|共同責任
使用者である獣医師を含む複数の獣医師が共同して診療を行った結果、獣医療過誤が生じた場合、診療に関与した獣医師のうち誰に過失があったのかを立証できなければ、診療に関与したすべての獣医師が連帯して責任を負います。
動物看護士に全責任がある過誤が生じた場合|不法行為責任
不法行為によって動物に被害が生じた場合の損害賠償の債務者は、損害を加えた獣医師です。
しかし、入院中の動物の世話をする動物看護師などに全責任がある不法行為であれば、当該動物看護士に責任があると同時に、使用者である獣医師も不法行為責任を負います。
まとめ
動物病院で獣医療過誤(事故)が発生した場合、診察を担当した獣医師だけでなく動物病院の経営者である獣医師も誠意ある対応をとるべきです。
獣医療過誤(事故)が発生した場合、その原因や病状の経過及び対応を正確に記録し、保存しておくことが重要です。本件では、使用者である獣医師BがAのカルテや検査結果を破棄していたため、獣医師側の主張を裏付ける客観的証拠が残っていませんでした。
カルテや検査結果を適切に記録・保存することは、勤務獣医師だけでなく使用者である獣医師(経営者)を守るものにもなり得ます。
獣医療過誤(事故)が発生したとき、どのような対応策をとるべきかを定め、勤務獣医師を含む動物病院のスタッフ全員に周知しておくことで、対象動物や飼い主への適切な対応も可能となります。
ネクスパート法律事務所には、獣医療に関する紛争につき豊富な知識を有する弁護士が在籍しております。獣医師やスタッフの皆様が安心して獣医療に取り組めるようサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
もしこのような被害に遭われた飼い主の方がいらっしゃいましたら、一般社団法人アニマルパーソンズへのご相談を推奨します。以下のバナーをクリックしてください。